
根よりすごい?大根葉の栄養と効能

大根といえば、煮ればおでんに味噌汁に主役級の働きをし、すりおろせば酵素たっぷり大根おろしで消化に優しい名脇役に…と、食卓に無くてはならない野菜ですよね!
大根の皮もきんぴらやお漬物にして食べられるし、「大根は捨てる部分が無い」と言われる程ですが、意外に忘れられがちなのが大根の葉っぱです。
「大根の葉」といっても、スーパーに並んでいる大根には葉がちょっぴりしかないものが多いので、どうせゴミになるからとキャベツの外葉なんかと一緒にむしってお店の生ごみ入れにポイ…なんて人、多いんじゃないでしょうか?
野菜が高騰して栄養バランスに頭を悩ませる日が続いているなら、それはすごく勿体ない!!大根葉は栄養の宝庫なんです。
お正月明けに売られている、七草粥が作れるセットを買ったことがある人はわかるかもしれませんが、春の七草の「スズシロ(清白)」は大根の別名です。昔から日本人の生活に、大根の根とその葉っぱが根付いているのがわかりますよね。

普段食べている大根の「根」の部分は淡色野菜ですので、大根=淡色野菜というイメージが強いと思いますが、実は「大根葉」は緑黄色野菜になるんですよ!
緑黄色野菜というと、かぼちゃやホウレン草といった色の濃い野菜がすぐ頭に浮かびますが、緑黄色野菜は色で分類されているわけではありません。厚生労働省では『可食部100gあたりのカロテン含有量が600μg以上の野菜』と決められています。
カロテンは赤や黄色の色素なので、色の濃い野菜の方が多く含まれている傾向があります。そのため、色の濃い野菜=緑黄色野菜という印象になっているようです。
緑黄色野菜ってネームバリューだけでも栄養がありそうな感じはしますが、思い切って普段食べている「根」の部分と栄養を比べてみちゃいましょう。
| 栄養成分 | 大根「根」(皮むき100g) | 大根「葉」(100g) |
|---|---|---|
| カロリー タンパク質 炭水化物 (内、食物繊維) ナトリウム カリウム カルシウム マグネシウム 鉄 カロテン ビタミンB1 ビタミンB2 ビタミンB6 ナイアシン 葉酸 パントテン酸 ビタミンK ビタミンC ビタミンE(α-トコフェノール) |
18kcal 0.4g 4.1g (1.3g) 17 mg 230mg 23 mg 10 mg 0.2 mg 0 0.02mg 0.01mg 0.05mg 0.2mg 33μg 0.11mg Tr 11mg 0 |
25kcal 2.2g 5.3g (4.0g) 48 mg 400mg 260mg 22 mg 3.1 mg 3900μg 0.09mg 0.16mg 0.18mg 0.5mg 140μg 0.26mg 270μg 53mg 3.8mg |
参照元: 日本食品標準成分表2015年版(七訂)
どうですか?差が少ないカリウムでも、大根葉なら根の約1.7倍で、カルシウムや鉄になると10倍以上摂れるという結果になりました。
緑黄色野菜の基準になっているカロテンは、根には全然含まれていないんですね…。葉では100gで3900μgですから、余裕で緑黄色野菜の基準をクリアです!
その他にも、ビタミンKとビタミンEは根では摂る事が出来ない栄養素なのがわかります。ちなみに「Tr」は、ゼロではないけど最小単位に満たない量ですから、この場合1μgに満たない極微量ということです。
ビタミンKは、正常に止血をするために必要になるほか、骨の健康を保つためにも欠かせない栄養素で、骨粗鬆症の薬としても使われています。
ビタミンEは強い抗酸化作用があり、活性酸素から体を守ってくれるので、生活習慣病や老化予防に効果があるとされている栄養素です。どちらも健康で若々しくいるためには、ぜひ摂っておきたい栄養素ですよね。
糖質制限ダイエットをしている人にとっては、大根葉のほうが炭水化物量が多いのは気になるところだと思いますが、よく内訳を見てください…大根葉は炭水化物のほとんどが食物繊維で、それを差し引いた糖質は1.3gです。
それに対して根の方は糖質が2.8gですから、糖質制限をしている人にも大根葉はオススメと言えます。
これを知ったら、もう「むしってゴミ箱へ…」なんてもったいなくて出来ません!同じ値段で葉付きの大根があったら、迷わず葉付きをゲットです。
ホウレン草より多いビタミン類
緑黄色野菜の葉モノ代表といえば、やっぱりホウレン草ですよね。ホウレン草で元気もりもりになるアニメもあったし、鉄分豊富で貧血にも良いし、みんなが良く知る健康野菜です。
大根の葉っぱとホウレン草…栄養素を比べたら流石にホウレン草が圧勝?いえいえ、大根葉も負けてないんです。
| 栄養素 | 大根葉(生100g) | ホウレン草(生100g) |
|---|---|---|
| β-カロテン ビタミンB1 ビタミンB2 ビタミンB6 ビタミンC ビタミンK ビタミンE(α-トコフェノール) ナイアシン パントテン酸 葉酸 カルシウム 鉄 カリウム マグネシウム |
3900μg 0.09mg 0.16mg 0.18mg 53 mg 270 μg 3.8mg 0.5 mg 0.26mg 140 μg 260 mg 3.1 mg 400 mg 22 mg |
4200μg 0.11mg 0.20mg 0.14mg 35 mg 270 μg 2.1 mg 0.6 mg 0.20mg 210 μg 49 mg 2.0 mg 690 mg 69 mg |
参照元: 日本食品標準成分表2015年版(七訂)
大根葉が勝っている栄養素を太字にしてみました。驚きなのは、鉄分が豊富なイメージの強いホウレン草より、大根葉の鉄分のほうが約1.5倍も多いというところです!
ビタミンCも約1.5倍・カルシウムは約5.3倍と圧勝ですから、貧血で悩んでいる人はもちろん、風邪をひきやすい人や、お肌と骨の健康に気をつけたい人にも、大根葉の方が効果が高そうですね。
ここではホウレン草も大根葉も生の状態の栄養素を比べましたが、ホウレン草は結石を引き起こすシュウ酸が多く含まれていますので、シュウ酸を摂りたくない場合や歯がキシキシする感じが苦手な人は、炒め料理でも一度茹でる必要があります。
茹でた時には、シュウ酸と一緒にビタミンCなど水溶性のビタミンが茹で汁に流れ出てしまったり、熱に弱い葉酸などの栄養素が減ってしまうことも考えられますので、調理次第で栄養効果も変わってくることは、ちょっと頭に入れておきましょう。
アンチエイジングに最適

ビタミンKにビタミンE・ビタミンCと健康で若々しくあるために摂っておきたい栄養素が出てきましたが、大根葉に含まれているアンチエイジングに効果がある栄養成分はそれだけではありません。
たくさん含まれているβ-カロテンにも嬉しい効果があるんです!β-カロテンというのは、体の中で必要に応じてビタミンAになるという特徴があるので、ビタミンAとしての効果とβ-カロテンとしての効果があり、1つで2度美味しい栄養素です。
ビタミンAとしては、お肌の新陳代謝を高める働きと粘膜を強化してくれる働きがありますので、瑞々しい美肌を作り、風邪などのウイルスから体を守るために役立ちます。
β-カロテンとしては、強い抗酸化作用がありますので、細胞を酸化させて老化や癌の原因になるとされている活性酸素から体を守る働きがあります。
β-カロテンは、同じく抗酸化作用があるビタミンCやビタミンEと一緒に摂る事で相乗効果が生まれ、抗酸化作用がアップするとされていますので、ビタミンCもEもしっかり含まれている大根葉は、アンチエイジングに最適な食材なのです。
 大根葉は乾燥すると栄養アップ
大根葉は乾燥すると栄養アップ
ドライフルーツや野菜チップスなんかの、乾燥させた果物や野菜って人気がありますよね。近年では「自宅で干し野菜を作ろう」と、ベランダに吊るせる干し籠がホームセンターなどでも売られていたりします。
実際天日で干した野菜は、アミノ酸の量が増えるので旨味が濃く、水分が減る分同じ量の生野菜と比べると、カルシウムや鉄分・カリウムなどのミネラルが多くなり、ナイアシンなどのビタミンもアップしています。
身近な干し野菜である干し椎茸は、太陽の効果でビタミンDが増えていますし、干した大根である切干大根は100gに食物繊維が21.3g・カリウム3500mg・カルシウム500mg…と少ない量でたくさんの栄養を摂る事が出来ます。
大根葉を干したものは、現代人には馴染みがありませんが、干した大根葉は『干葉(ひば)』や『かけ菜』と呼ばれ、古くは緑黄色野菜が少ない季節の貴重な保存食として食べられていました。
葉付きの大根を買った場合、そのままにしておくと根の部分がすぐにシナシナになってしまうので、根と葉をすぐに切り離す必要がありますが、切り離した大根葉は3日程度しか持ちませんし、結構かさばります。
そこで大根葉を干して乾燥させる事で、長期間保存することができるようになり、カサは減っているのに旨味も栄養価も高くなって最高の保存食になります。
食べる時には水やお湯で戻せば簡単に美味しく食べられますので、大根葉を手に入れたら是非干してみてくださいね!
大根の葉の干し方
【茹でずに干す干し方】
- 大根葉を良く水洗いし、汚れや虫をしっかり落とす
- ざる等に広げるか、物干し竿に吊るして風通しの良い場所に干す
※大根葉が重なっているとカビが生えやすいので注意 - 天気と湿気に注意して時々裏返し、半日~1日ほどで半生(セミドライ)・カラカラに乾燥させたい場合は様子を見ながら3日以上干す
【茹でて干す干し方】
- 大根葉を良く洗い、塩を少し入れたお湯で硬めにサッと茹でる
- 硬く絞ってざる等に広げるか、物干しざおに吊るして風通しの良い場所に干す
- 天気と湿気に注意して時々裏返し、半日~1日ほどで半生(セミドライ)・カラカラに乾燥させたい場合は様子を見ながら3日以上干す
セミドライの大根葉は、細かく刻んで真空パックに入れ、冷凍保存しておけば1ヵ月~3カ月ほど保存することが出来ます。
食べる時は水で戻し、そのままお味噌汁の具として使えるほか、煮物や炒め物の色どりとして使ったりと手軽に幅広く使うことが出来ます。
茹でずに干した方が栄養の損失は少なく、大根葉の風味も濃く仕上がりますが、苦みや辛みが気になる人は茹でてから干すと和らぎます。
カリカリに乾燥させた場合は、乾燥材と一緒に密閉容器に入れておけば半年~1年とかなり長期保存出来るようになります。体積も減って保存スペースも少なくて済みますので、大量に大根葉がある場合にオススメです。
喉に良い!大根葉茶の作り方
喉が痛い時や咳が出る時なんかに、大根を水あめや蜂蜜に漬けて出た汁を飲む…という民間療法は結構有名ですよね。小さい頃お母さんやお婆ちゃんが作ってくれたって人もいるのではないでしょうか?
大根は根も葉も種子も、昔から薬効があるとして民間療法に多く使われていて、種は今でも「萊菔子(らいふくし)」という名前で漢方などで薬用として使われています。
大根葉は、『肺や喉の熱をとり、喉の腫れを解消して調子を整える』とされていますので、喉の調子が悪い時には干した大根葉で作った「大根葉茶」を飲めば、薬に頼らず体に優しい喉対策が出来ますよ。
【大根葉茶の作り方】
- 良く水洗いした大根葉を、カリカリになるまで陰干しする
※大根葉茶にしたい場合はセミドライではなく完全に乾燥させます - 乾燥させた葉を細かく砕いて瓶など清潔な密閉容器に保存
※少ない場合は手やハサミでも細かく出来ますが、たくさん作りたい場合はミルやフードプロセッサーを使うと便利です - 急須で作る場合は乾燥葉を入れ、70℃くらいのお湯を入れて栄養素が溶け出るまでじっくり待てば出来上がり
- たくさん飲みたい場合は、やかんに乾燥葉30g・水1ℓを入れて水から5分程煮出せば出来上がり
乾燥させた大根葉である、干葉を煮出した「干葉湯」は冷え症や婦人病に効果があるとされていますので、お茶として飲むのはイマイチだった…という場合でも、煮出したお湯をお風呂に入れて腰湯としても活用できます。本当に無駄がないですよね!
 栄養満点!じゃこと大根葉のふりかけ
栄養満点!じゃこと大根葉のふりかけ
大根葉のメジャーな食べ方といえば、じゃこ(又はしらす干し)と一緒に炒めたふりかけですよね!生の大根葉を下茹でして作るのが一般的ですが、干して乾燥させた大根葉でも作ることが出来ます。
セミドライの大根葉ならしっとりとしたふりかけになり、カラカラに乾燥させた大根葉なら水分が少ない分保存出来る期間が長くなりますので、好みに合わせて作ってみてくださいね。
カルシウムも摂取!大根葉のふりかけ

大根葉単品でもカルシウムが豊富な食材ですが、ふりかけの材料にじゃことゴマを加えることで、よりカルシウム満点のふりかけを作ることが出来ます。
ちりめんじゃこは鰯の小魚なので、カルシウムも多く魚の栄養が丸ごと摂れますし、ゴマには100gで1200mgのカルシウムが含まれています。
骨粗鬆症予防にカルシウムを摂りなさい…と言われても、なかなか毎日魚料理を作るのは大変ですよね。大根葉とじゃこのふりかけを作っておけば、お弁当やおにぎりの具としても使えますので、無理なくカルシウムと大根葉の豊富な栄養が摂れて、忙しい人にもオススメです!
【材料】
乾燥大根の葉 1本分
鰹節 1パック
じゃこ 大さじ3~4(お好みで)
白煎りゴマ 大さじ1
麺つゆ 適量
【作り方】
- 干した大根葉はみじん切りにする
- フライパンにごま油を熱し、じゃこを入れてカリッとするまで炒める
- 白煎りゴマ・大根葉を入れて炒める
- 味をみて麺つゆで味付けし、鰹節を加えて水分が飛ぶまで炒めたら出来上がり
※大根葉の量とじゃこの塩気によって麺つゆの量は加減してください。他に干し海老や乾燥わかめなどお好みの食材でアレンジすると飽きずに食べられますよ。
ビタミンAの吸収アップ!大根葉の油炒め
大根葉に多く含まれているβ-カロテンは、水には溶けず油に溶けやすい性質があるため、油と一緒に摂ると体に吸収しやすくなる栄養素です。
ビタミンAも脂溶性ビタミンで、加熱に強く油と一緒に調理して食べると吸収率が良くなりますので、β-カロテンとビタミンAの効果を最大限に摂りたい場合は油で炒めて調理する方法が一番です。
大根葉は油揚げとの相性も良いので、ふりかけを作る時の材料に油揚げを1枚加えて、麺つゆやみりんで溶いた味噌で炒め煮にするとふりかけよりも満足感のあるおかずに仕上がります。
ちなみにビタミンEとビタミンKも脂溶性ビタミンですので、大根葉を加熱調理して食べたい場合には、お味噌汁でも油揚げを足したり、ちょっと油を加えた方が、ただ煮たり茹でたりするよりも栄養の吸収面では優れているといえます。
青汁の発祥が大根の葉だった
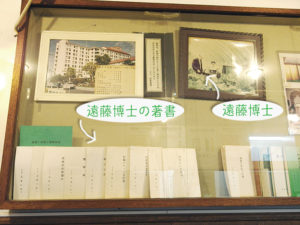 今では健康飲料の代名詞ともいえる青汁ですが、意外にその始まりは古く、健康ブームよりもっと昔…戦時中の食糧難にまでさかのぼります。
今では健康飲料の代名詞ともいえる青汁ですが、意外にその始まりは古く、健康ブームよりもっと昔…戦時中の食糧難にまでさかのぼります。
青汁の父と呼ばれる、医学博士の遠藤仁郎先生は、戦時中の食糧難による空腹と栄養状態の悪さをなんとかしようと、当時大根を収穫した後畑にそのまま捨てられていた葉を、拾って食べることを思いついたのがその始まりと言われています。
最初は大根葉や里芋の葉などを乾燥させて保存食にしたり、油で炒めて空腹をしのぐために食べていたものが、生で食べたらもっと効果があるのでは?と搾り汁にして飲むことを思いつき、それが奥様の命名で「青汁(あおしる)」となって現在の青汁に繋がっていきます。
今は青汁はお金を出して買うのが普通ですが、最初は捨てられている大根葉から始まったというのは驚きですよね!
自分たちの家族で大根葉など、菜っ葉の健康効果を実感し、周りの人にも広めていった…という、今でいうなら「口コミ式」で広まったというのもビックリです。
商売としてではなく、身近にタダで手に入るもので栄養が摂れるよ!と教えてくれたからこそ、試す人も多くて沢山の人に広まったのかもしれませんね。
そんな「始まりの大根葉」ですから、手作り青汁の材料としても適しています。ただ根と同じく葉にも辛みがありますので、辛みが気になる場合には蜂蜜を足すと辛みが和らぎます。
生の大根葉には、加熱をすると摂れなくなる酵素や、酸化しやすいビタミンCがたくさん含まれていますので、新鮮な大根葉が手に入った時には、青汁の歴史に思いを馳せつつ、手作り青汁を作って飲んでみるのも良いかもしれませんよ?

